『近頃の若者はなぜダメなのか~携帯世代と「新村社会」~』 原田曜平 (博報堂ブランドデザイン若者研究所リーダー)
発行:2010年1月 光文社新書
難易度:★☆☆☆☆
資料収集度:★★★★☆
理解度:★★★★☆
個人的評価:★★★★☆
ページ数:262ページ
【本のテーマ】
最近の若者はダメになったのか?「ケータイ・ネイティブ」である若者の人間関係はどう変わったのか、全国津々浦々の若者約1000人との個人対話を通して明らかになった、世代論を超えた「時代論」。
【キーワード】
コミュニケーション、空気を読む、キャラ、新村社会、ケータイネイティブ世代、
ネットワーク格差社会、既視感
ネットワーク格差社会、既視感
【目次】
第一章 ”読空術”を駆使する若者たち――KY復活現象の謎
第二章 知り合い増えすぎ現象――”新村社会”の誕生
第三章 村八分にならないためのルール――新村社会の掟と罰
第四章 半径五キロメートル生活――若者を覆う「既視感」の正体
第五章 ちぢこまるケータイネイティブ――若者はなぜ安定を望むのか?
第六章 つながりに目覚めた若者ネットワーカー――新村社会の勝ち組とは?
第七章 近頃の若者をなぜダメだと思ってしまうのか?――世代論を超えて
謝辞
「ある男子大学生の《1週間、全送受信メール》」
【概要】
はじめに
著者が博報堂の若者研究所に配属され、若者調査を開始したころの話、
若者が「空気を読む」ことの敏感になっているということに気付いたエピソードが書かれていた。
第一章 ”読空術”を駆使する若者たち――KY復活現象の謎
昔と比較して、言語的コミュニケーションの能力は低くなっているように思われるが、
曖昧さを理解するコミュニケーション能力は高まっている。例)内閣府調査「気の合わない人とでも話ができる」小中学生が2000年32%→2007年41%へ増加、
「コミュニケーション」は、「エコ」や「健康」などの流行のテーマと並ぶようになってきている。
若者へのインタビューや講演依頼を通して、若者が「キャラ」を通して、求められている自己像を演じる気遣いをしていると感じたエピソードを例に、今の若者の間では、本当の自分を無防備にさらけ出す行為はタブーで、相手の表情や場の空気を読んで、相手の望むキャラになることが、マナーや礼儀作法になっている。と述べていた。
『「空気」の研究』(著:山本七平)が1977年に出版されているように、昔から日本人には「空気」を重視する文化が根付いていた。高度成長からバブル経済に向かう中で自由や個人化が叫ばれ、地域共同体(村社会)の衰退により、「空気を読む」文化は徐々に廃れ、過去の産物になったのかと思われたが、実は、単に一時的に影を潜めていただけである。バブル崩壊と、後述する「新村社会」の登場により、再び「空気を読む」文化が再認識されるようになった。国語辞典制作者の金田一秀穂は、上記の意味で、「今の日本の若者はもっとも日本人らしい日本人である」と述べていた。
第二章 知り合い増えすぎ現象――”新村社会”の誕生
日本経済新聞2008年4月9日によると、日本の高校生の96.5%が自分専用の携帯電話を持っており、6~8割であったアメリカ、中国、韓国を大きく引き離した。
ドコモ・モバイル社会研究所調べによると、10代は14.24歳(中学2・3年)、20代は16.77歳(高校1・2年)から携帯を持ち始める。このような「ケータイネイティブ世代」は、かつての若者が経験したような、連絡を取れない苦労することが減った。携帯を何に利用しているかは、10代、20代ともにSNSがトップであった。(10代:24.8%、20代:30%)、ケータイ電話帳の登録人数(平均)は、40代でも159.0人であるのに、10代ですでに93.4人、20代で135.0人、30代で139.6人と、非常に広範囲な人間関係を形成する役割を担っている。また、電話以外にも、グループや、メーリングリストなどで、複数のグループに同時に登録している若者が多い。この人間関係の広まりにより、一人ひとりとの交流の質は昔と異なり、お互いの家族構成や現在の恋愛事情を知らないけれども「親友」である、という状況が生まれるようになった。基礎情報よりも、キャラ情報の方が重要になった。それにつれて、若者の消費は、「安い値段を多くの回数で」行われるようにと変化した。また、浅い人間関係が広く結ばれるようになったため、かつての義務性と継続性のある、「村社会」のような「監視社会」的性質が強まってきたため「空気を読む」文化が再認識されるようになった。と述べていた。
この「新村社会」は、拘束力があるうえ、かつての村社会よりも人的規模が圧倒的に多くなった。
第三章 村八分にならないためのルール――新村社会の掟と罰
①愛想笑いを絶やしてはいけない。・・・リアル、メール・ブログ上ともに愛想笑いを絶やしてはならない。
②弱っている村人を励まさなくてはいけない。・・・「鬱日記」や「病み日記」を書く人がいたら、励ましてあげるのがマナー。ただし、頻繁にそのような投稿をする人は、「KY」として、徐々に距離を置かれるようになる。
③一体感を演出しなければならない。・・・感情を共有しやすい便利な感嘆詞「やばい」や、グループ内で通じる隠語。等を使い、一体感を演出する。
④会話を途切れさせてはならない。・・・「即レス」がマナー。
⑤共通話題をつくりださないといけない。・・・趣味・嗜好が多様化してきたため、意識的に共通話題(「時事ネタ」等)を探さないといけない。
⑥「正しい事」より「空気」に従わなくてはいけない。・・・山本七平の「抗空気罪」、論理的判断と空気的判断の二重基準で物事をとらえなくてはならない。
⑦コンプレックスを隠さなくてはいけない。・・・周りに合わせないといけないため、コンプレックスは隠さないといけない。
⑧「だよね会話」をしなくてはいけない。・・・議論をして、相手の意見を否定したり批判するよりも、正解不正解のない「未来」の話などをする。
⑨恋人と別れてはいけない。・・・別れた後もSNSなどで共通の知り合いを通して繋がっているため、悪い噂に発展したり、過去の情報を流されたりし、「分別れるリスク」が大きい。
以上あげた、「新村社会」のルールから、逃れるための方法として、「キャラ立ち」がある。
周りから認められる「キャラ立ち」に成功すれば、空気を読まない言動でも許される。
例)オレオレキャラ(ナルシスト)、ぶりっ子キャラ、関西キャラ、介護キャラ、島根キャラ、洋服キャラ、「KY」キャラ、など。「キャラ立ち」があるわけでもなく、空気を読まなかった人は、「村八分」にされる。「村八分」とは、昔の「規約違反した者を、葬式と火災の二つの場合を例外して絶交する」という風習であり、「新村社会」における「村八分」とは、量的に人口規模の上で大きな違いがあり、質的には、ネット上の非現実部分でも被害を被るという点で異なっている。「新村八分」の特徴として、①晒される・・・個人情報をネットに流される②村十分・・・逃げ場のない徹底的な疎外。③縦社会の崩壊・・・対象が目上の人にまで及ぶ。④親も参加する。の4つをあげていた。
第四章 半径五キロメートル生活――若者を覆う「既視感」の正体
人間関係が広くなる現象がみられる一方で、行動範囲が極端に狭い若者も多くみられる。その原因として、ネット上の情報を見ることにより「既視感」を感じ、経験したことのないことを、経験したような気になってしまうからである。と述べていた。東京都内においても、非常に狭い行動範囲内で生活し、渋谷などの繁華街に行きたがらない若者が多く存在していると述べていた。
第五章 ちぢこまるケータイネイティブ――若者はなぜ安定を望むのか?
ネットで検索し、数個の情報に目を通すだけで、「理解した」と思う傾向がある。例)大学のレポートのコピペ(協力したわけでもないのに、内容がほとんど同じ生徒が何人もいた。)知識にとどまらず、価値観も大人の受け売りを鵜呑みにしがちであり、そのため、「平成的リスク」よりも「昭和的安定」を望む若者が多い。
第六章 つながりに目覚めた若者ネットワーカー――新村社会の勝ち組とは?
ネットワークの広まりにより、大人以上にネットワークを活用する若者が増えた。大規模人数のイベントを行ったり、立場や所属の違う人々で集まることを可能にした。そのことにより、かつては異文化であった様々な文化が融合するようになり、(例:オタク文化とギャル文化、がり勉とジャニーズ系)生活階層の上流、下流の交流が盛んになり、階層間の移動も流動的になった。「新村社会の勝ち組像」として、生活階層が上流、下流どちらともバランスよくつきたい、下流からはファッションや異性の口説き方などを学び、上流からは、競争的な環境を得る、どちらに偏ることもない関係を築くことである。と実例を交えながら述べていた。また、生活階層が下流である若者も、SNSなどのネットワークを利用することによって、世界や視野を広めていくことができる可能性が増えた。ということを実例を通して述べていた。このように、ネットワーク形成能力が今後より人生において重視されていくと考えられるため、今後「賃金格差」から、「ネットワーク格差」により格差が論じられていくのではないか、と述べていた。
第七章 近頃の若者をなぜダメだと思ってしまうのか?――世代論を超えて
この章までの総括を行っていた。
ケータイネイティブは、SNSなどのサービスを利用することにより、広く浅い、しかし継続的な人間関係である「新村社会」を形成し、その中で「空気を読み」ながら関係を維持している。新村社会は、その村人の口コミにより、「既視感」を強めることになり、行動範囲を狭める要因にもつながっている。しかし、その反面、意志と行動力さえあれば、「地域・偏差値・年代」を超えて有機的に人とつながっていけるようになった。そして、前者と後者の間に「ネットワーク格差」が生まれるようになった。
若者を語る際は、「若者批判」か「大人・社会批判」のどちらかに偏ってしまいがちであるが、若者の現状を見つめようとする姿勢を持ち続け、「世代論」を決めつけや思い込みにしてしまわず、「時代論」(携帯やSNSの登場は他の世代にも影響を与えている。)としてとらえられるような視点が必要である。
【感想】
「さとり世代」と同じ著者が書いた本を読みました。
若者に直接インタビューを行い、若者の現状をとらえようとする。というのは、実践的な社会調査であり、現実味のあるリアルな実態であると思いました。しかし、発行が2010年であり、調査はそれ以前に行われていることを考慮すると、もうすでに、「ひとむかし前の若者論」であることは否めない。と思いました。(LINEが登場していない)しかし、現在にも十分通じる部分が多かったです。
「空気を読む」文化が以前からあり、バブル時代の時だけ影を潜めていた、という主張は、
斬新であり、しかし、納得のいくものでした。
また、若者が「空気を読み」、その場で求められている「キャラ」を演じる、という表現が、現在の若者をリアルに描いていると思い、しかしそれが「日本人らしい」現象であるという指摘にも、考えさせられました。
「ネットワーク格差」という言葉も、革新的で、しかし、的確であると思いました。
今後も、ネットワークをうまく築ける人と、うまく築けない人との間に、情報的にも、生活の質的にも、大きな差が生じて来るだろうと簡単に想像できました。
しかし、いたずらにネットワークを広めることだけを意識したがる若者というのも問題だと思います。例えば、Twitterのフォロワー数を競い合うように増やしたりする若者とか。
「新村社会」の特徴は「広く浅く」ではあっても、その中にも継続性があり、それぞれの人ときちんとそれぞれの「関係」が存在していることが前提であると思うので、無駄に増やしすぎても、その人たちと最低限の「関係」も築けていないと、それはあまり意味がないのではないかな、と思います。そのような若者像は描かれていなかったので、2010年以降になって登場してきたのかな。と、想像しました。
【個人的評価・理解度】
文体は非常に読みやすく、サクサク読み進められました。
「空気復活論」は斬新であり、説得力があるので、卒論にも取り入れたいと思いました。
ケータイネイティブは、SNSなどのサービスを利用することにより、広く浅い、しかし継続的な人間関係である「新村社会」を形成し、その中で「空気を読み」ながら関係を維持している。新村社会は、その村人の口コミにより、「既視感」を強めることになり、行動範囲を狭める要因にもつながっている。しかし、その反面、意志と行動力さえあれば、「地域・偏差値・年代」を超えて有機的に人とつながっていけるようになった。そして、前者と後者の間に「ネットワーク格差」が生まれるようになった。
若者を語る際は、「若者批判」か「大人・社会批判」のどちらかに偏ってしまいがちであるが、若者の現状を見つめようとする姿勢を持ち続け、「世代論」を決めつけや思い込みにしてしまわず、「時代論」(携帯やSNSの登場は他の世代にも影響を与えている。)としてとらえられるような視点が必要である。
【感想】
「さとり世代」と同じ著者が書いた本を読みました。
若者に直接インタビューを行い、若者の現状をとらえようとする。というのは、実践的な社会調査であり、現実味のあるリアルな実態であると思いました。しかし、発行が2010年であり、調査はそれ以前に行われていることを考慮すると、もうすでに、「ひとむかし前の若者論」であることは否めない。と思いました。(LINEが登場していない)しかし、現在にも十分通じる部分が多かったです。
「空気を読む」文化が以前からあり、バブル時代の時だけ影を潜めていた、という主張は、
斬新であり、しかし、納得のいくものでした。
また、若者が「空気を読み」、その場で求められている「キャラ」を演じる、という表現が、現在の若者をリアルに描いていると思い、しかしそれが「日本人らしい」現象であるという指摘にも、考えさせられました。
「ネットワーク格差」という言葉も、革新的で、しかし、的確であると思いました。
今後も、ネットワークをうまく築ける人と、うまく築けない人との間に、情報的にも、生活の質的にも、大きな差が生じて来るだろうと簡単に想像できました。
しかし、いたずらにネットワークを広めることだけを意識したがる若者というのも問題だと思います。例えば、Twitterのフォロワー数を競い合うように増やしたりする若者とか。
「新村社会」の特徴は「広く浅く」ではあっても、その中にも継続性があり、それぞれの人ときちんとそれぞれの「関係」が存在していることが前提であると思うので、無駄に増やしすぎても、その人たちと最低限の「関係」も築けていないと、それはあまり意味がないのではないかな、と思います。そのような若者像は描かれていなかったので、2010年以降になって登場してきたのかな。と、想像しました。
【個人的評価・理解度】
文体は非常に読みやすく、サクサク読み進められました。
「空気復活論」は斬新であり、説得力があるので、卒論にも取り入れたいと思いました。
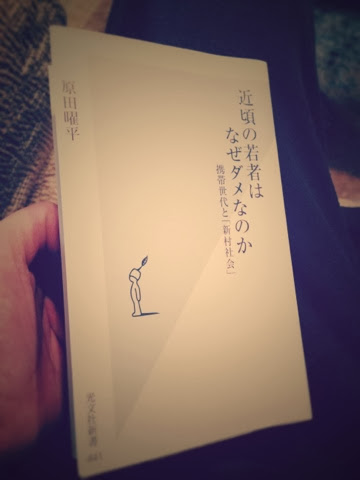
0 件のコメント:
コメントを投稿